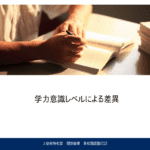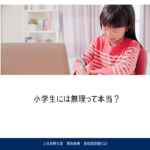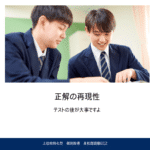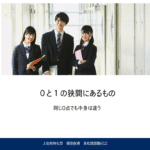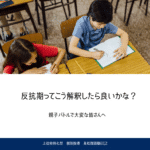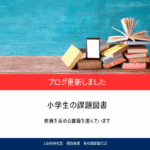高松市国語塾EQZ塾長です。
今回は小学生対象の「教養読書の会」のお話です。
読解を行う上で、教養は非常に重要です。読解の一番下の土台を支えているものだと解釈しています。
塾生の80%以上が、高松高校・高松一高校に合格する高松国語塾EQZのインスタグラム
塾だから読める
子どもたちは、塾に備えてある書棚から好きな書籍を手にとります。書籍ラインアップは僕の選択です。物語も多少ありますが、基本的には「興味関心が広がるもの」という指針で選択しています。
見るからに子供が好みそうな表紙やタイトルを持つ物語とは違って、少しとっつきにくい面はあるかもしれません。「易経」「日本国憲法」「神話」「哲学」「科学」等々、普段なら見向きもしないタイトルかもしれません。
でも、読みます。塾だから読めるのです。しかも超集中して読めるのです。
そして、1週間に1つのテーマについての教養が広がっていくのです。
趣味の読書と異なる点
生徒があるテーマについて読んだら、
「語句の意味調べ」
「この本を読んで新たに学んだこと」
「この本を読んで感じたこと、考えたこと」
等を記述してもらいます。
ここですね。ポイントは。趣味で読む読書と大きく異なる点は。
アウトプットを念頭に置いた読書なのです。
趣味で読む読書が悪いとは全くいうつもりはありません。読書が好きならどんどん読めば良いです。ただ、それを学習効果につなげていくためには、アウトプットが欠かせないと思います。
お互いに教養を高める
生徒が選んだ本の内容に対して、少しずつコメントや解説を入れるようにしています。最近ですと……
「島流し」の話をしました。
「死刑制度」の話をしました。
「税金」の話をしました。
「光の速度」の話をしました。
「電磁波と周波数」の話をしました。
「落語」の話をしました。
「ロボット」の話をしました。
塾長も様々な話題についていくのです。もちろん全部が全部わかるわけではありません。時にはググって、画像や映像も出して、理解してもらうようにしています。ググったりする中で塾長自身も教養が高まってきて、それをまた生徒たちに還元できるのです。
抽象語力
更に、今年度から取り組んでもらっているのは、抽象語の獲得です。
指定した抽象語の意味を調べ、例文を調べ、それを元に自分で例文を作ってみることです。
意識しないと、抽象語の力は増えません。
日常生活では不要な語、使わない語も多いからですね。
だからこそ、意識して獲得していく必要がある思います。
まずは、【国語ができる子にするために必要な具体策を提示する保護者説明会】にお越しください。
次回は12月17日(日)10:00~12:00で開催します。
入塾の勧誘なんかしていませんから。中身がないことがばれて生徒が減って大変な大手塾とは違いますから。一緒にしないでほしいと思います。