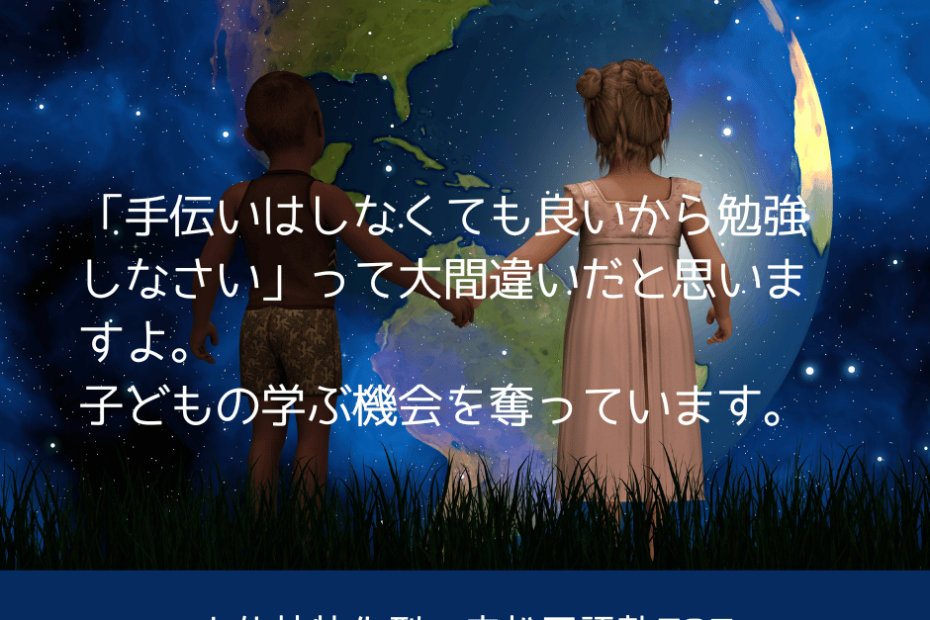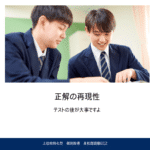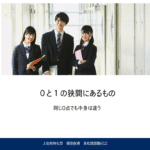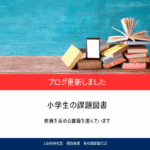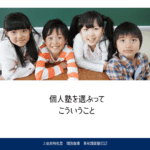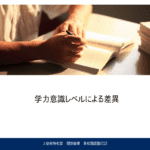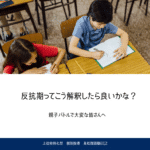高松市国語塾EQZ塾長です。
国語ではなく、道徳の時間のタイトルみたいになってしまいました。
塾生の80%以上が、高松高校・高松一高校に合格する高松国語塾EQZのインスタグラム
お手伝いの意義
「お手伝いをしましょう」と語られる割には、その意義はあまり語られていない気がします。
子どもが家庭でお手伝いをすることは、僕は賛成なんですね。なぜかと言いますと……
お手伝いは「世の中を知ること」につながると思っているからです。単に「作業」で終わらせてしまうのはあまりに勿体ない気がします。
親御さんの手伝いをすることによって、親子のコミュニケーションが増える、終わった時の充実感を味わう、等の要素もあることと思います。それはそれで良いと思います。
ただ、最も主な意義は、
「身の回りのことから世の中のことを知るきっかけ作り」
にあると思います。
方法を知る
手伝うことによって、知ることもたくさん出てきます。その一つは、「方法」です。
「方法」を知ることは、生きる力にも繋がりますよ。
掃除の方法、洗濯の方法、皿洗いの方法、調理の方法、片付けの方法、これら生きていく上でうえで必須アイテムでしょう。
「方法」を知るためには、実際にやってみることはもちろん必要ですし、方法を学ぶことによって新たな知識も増えるはずです。
中学生にもなって、ご飯が炊けない、みそ汁作れない、掃除ができない、ゴミ出しが分からない、という子がいるみたいですよね。驚きです。
勉強以前に、世の中を生きていないわけですね。
「あなたは、お手伝いしなくても良いから勉強しなさい」を言い換えると、「世の中を知らなくても良い」という意味でもあります。
親が、子どもの学ぶ機会を奪っているといっても良いでしょう。
背景を知る
手伝いをする中で、お子さんにその背景を教えてあげてください。
ゴミはなぜ分別するのか? ◎◎を捨てるときはどうするのか?
皿洗い、様々な大きさ形の食器の使い方はどうなのか? また、それぞれの食器は何でできているのか? この食器は割れるけど、こっちは割れない、それはなぜなのか?
洗濯はなぜするのか? しないと一体どうなるのか? 晴天と雨天では乾き方はどう違うのか? どういう干し方が良いのか?
この食材とあの食材は何が違うのか? 元は何からできているのか? その原料はどうなっているのか? 炊く、煮る、茹でる、沸かすとは何が違うのか? 焼く、炒めるは何が違うのか?
等々、身近な世のなかを教えてあげてほしいのです。いずれ、お子さんは一人で生きていかなくてはならないのです。自立した生活ができるために、まずは身の回りのことを教えてあげましょう。
それは「何か」につながっていきますよ。
繋がっていくこと
「何か」につながる、とはかなり抽象的でしたね。
例えば、陶器の食器、ガラスの食器、プラスチックの食器の違い、原料などを教えたとします。そこから興味を持って、土の研究が始まるかもしれない、ということです。同じ「土」なのに、なぜこうも違ったものができ上るのか?という興味を持ってくれるかもしれません。そこから発展して地層に興味を持つかもしれません。地層を調べているうちに、化石に興味を持つようになるかもしれません。
逆に、何も発展しないかもしれません。別にそれはそれで良いのです。全てのことに興味を持つわけではありませんから。
でも、「何か」がないと、その先の「何か」は生まれないですよね。
これを「視野が狭い」というのです。
お子さんの学力向上を真剣に考える親御さん限定の説明会です。
12月17日(日)10:00~12:00開催です。